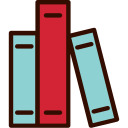冷血動物と温血動物の違い
目次:
主な違い–冷血動物と温血動物
生物は、体温を周囲の温度で調節する能力に基づいて、大きく2つのカテゴリに分類できます。これらの2つのカテゴリは、冷血(外温)動物と温血(吸熱)動物です。 NS 主な違い 冷血動物と温血動物の間には、 冷血動物は一定の体温を維持できませんが、温血動物は一定の体温を維持できます。 このため、彼らの体は周囲の温度に対して温度を調節するためにさまざまな適応を示しています。冷血動物と温血動物の違いについては、この記事で詳しく説明します。

冷血動物とは
冷血動物または外温動物は、周囲の温度の変化に応じて一定のレベルで温度を調節する生物です。代謝率は体温に直接依存するため、これらの生物の活動は周囲の温度に大きく影響されます。一般に、周囲の温度が下がると活動が低下し、その逆も同様です。代謝率は、体内で生成されるエネルギーではなく、主に熱または環境からのエネルギー獲得によって調節されます。このため、冷血動物のほとんどは温かい生息地で見られます。寒い生息地に住む動物は、通常、動きが鈍いです。冷血動物は、日光浴、体色の変化、日光の下で手足を伸ばすなど、体温を上げるためのさまざまな適応を示します。非常に寒い季節には、冷血動物は非常に不活発になります。たとえば、特定のカエルの種やサンショウウオは冬の間は動きません。ほとんどの昆虫は、飛翔筋の温度が最適な温度に上昇するまで飛ぶことはありません。多くの動物、特に両生類、爬虫類、魚などの脊椎動物は冷血動物です。

マウス(温血)を食べるヘビ(冷血)のサーモグラフィ画像
温血動物とは
温血動物は吸熱としても知られています。これは、環境の温度変化にもかかわらず、自分の体温を作り出すことができることを意味します。それらは、主に代謝プロセスと、発汗、あえぎ、断熱、四肢への血流の調節、移動、冬眠、穴掘り、体表面積と体体積の比率の変化などの適応メカニズムによって、35〜40°Cの一定の体温を維持します。これらのメカニズムのために、暖かい血の動物は非常に適応性があり、凍るような北極圏から最も暑い砂漠までの幅広い環境温度の中で生きることができます。したがって、温血動物は世界のほぼすべての生息地で見られます。哺乳類と鳥は温血動物の唯一のグループです。冷血動物と比較すると、温血動物は代謝率が高いため、エネルギー消費量が非常に高くなります。

コア温度の関数としての温血動物(哺乳類)と冷血動物(爬虫類)の持続的なエネルギー出力
冷血動物と温血動物の違い
意味
冷血動物: 冷血動物は一定の体温を維持することはできません。
温血動物: 温血動物は一定の体温を維持することができます。
エネルギー生産
冷血動物: 冷血動物は常に体温を調節するために熱の形でエネルギーを獲得します。
温血動物: 温血動物は体内で熱を発生する可能性があります。
熱源
冷血動物: 冷血動物は周囲の環境を通して熱を獲得します。
温血動物:温血動物は主に食物の消費を通じて熱を発生します。
代謝率
冷血動物: 冷血動物の代謝率は、環境温度の変化に伴って常に変化します。冷血動物の代謝率は通常、温血動物の代謝率よりも低いです。
温血動物: 一般的に、環境温度は温血動物の体温に大きな影響を与えません。
体温
冷血動物: 冷血動物の体温は周囲の温度によって異なります。
温血動物: 温血動物の体温は通常35〜40°Cです。
熱調節
冷血動物:冷血動物は、日光浴、体の色の変化、日光の下で手足を伸ばすなど、さまざまな方法で熱を調節します。
温血動物: 温血動物は、主に代謝過程と、発汗、あえぎ、絶縁、四肢への血流の調節、移動、夜間活動、冬眠、穴掘り、体表面積と体体積比の変化などの適応メカニズムによって熱を調節します。
例
冷血動物: 魚、爬虫類、両生類、昆虫などは、冷血動物の例です。
温血動物: 哺乳類や鳥は温血動物の例です。
画像提供:
「ウィキヘビはネズミを食べる」アルノ/コーエン– www.nutscode.com(CC BY-SA 3.0)コモンズウィキメディア
「Homeothermy-poikilothermy」PetterBøckman著– Commons Wikimediaによる自作(パブリックドメイン)